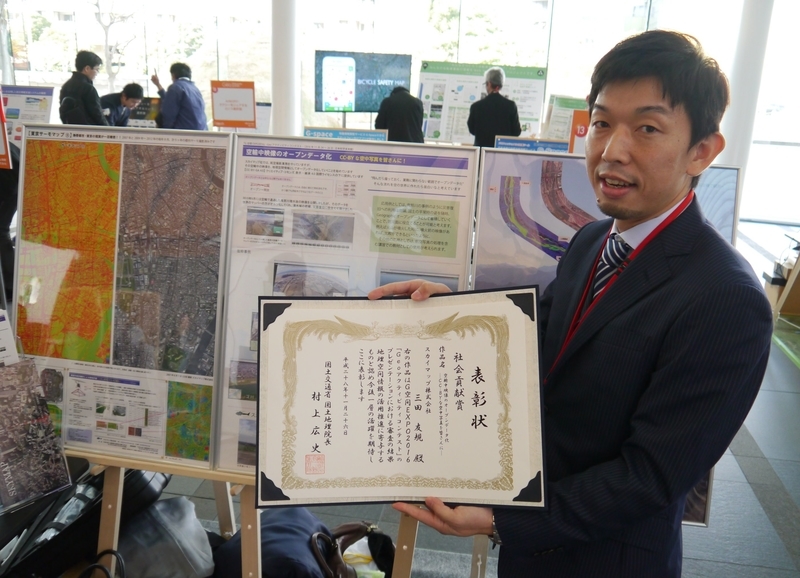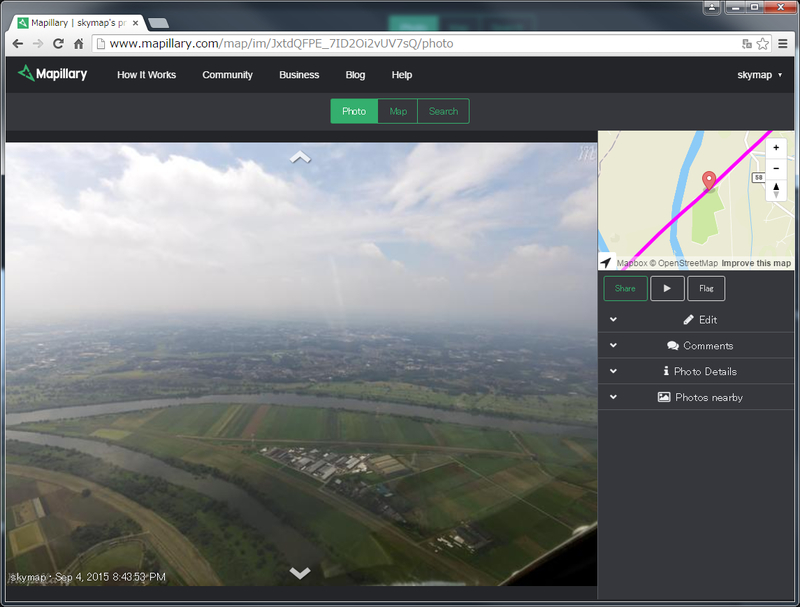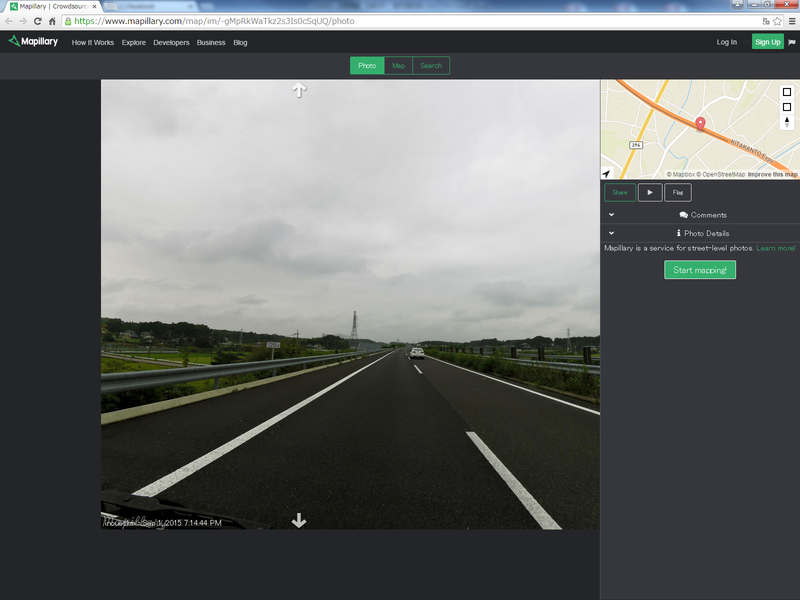今年は夏の三大風邪の1つ、手足口病が大流行のようです(※)。
大人は感染確率0.6%だそうですが(※)、見事に当選をし、先日、感染してしまいました。あまり事例もなさそうなので、以下、記録までに私の症例を。
40度の高熱が3日続く。最初の発熱は、一瞬で平熱→40度まで上がった感じでした。普通に夕食を食べた後に急に寒気がして、測ってみると40.3℃!座薬もすぐに効果がなくなるほど熱源は強かったです。
40度の高熱が3日続く。最初の発熱は、一瞬で平熱→40度まで上がった感じでした。普通に夕食を食べた後に急に寒気がして、測ってみると40.3℃!座薬もすぐに効果がなくなるほど熱源は強かったです。
2日目(高熱2日目)、内科にいって、尿検査、血液検査するも異常なし。
3日目、手足に少し発疹が出てきて、まさかとは思い、もう一度、内科に。「手足口病」ですねと。午後から、だんだん熱は下がり微熱状態に。一方で、足の発疹がだんだん増えてきて歩くと痛む。夜中、汗をひどくかいて何度も着替える。ベロがカサカサ、全く水気のない状態。ザラザラとかでなくて、カッサカサ。
4日目、起きると高熱はひいていて身体は楽。ただ、ここからがこの病気の本番だった。手の発疹は痛いし、足のはもっと痛くてふわふわのマットの上でしか歩けないし、口(舌と喉)が痛くて、ざる蕎麦をミキサーして食べる始末。ざる蕎麦をミキサーにかけて、スプーンで食べると、そばがきっぽくて、乙ではあったが、食事の楽しみを奪われた日々はしんどかった。
5日目、足(足首より下)がとにかく痛む。なったことないけど、全体が霜焼けみたいに腫れ上がっていた。あと、内ももや、肘の裏、お腹にも薄い斑点がでてくる。
6日目、足と口内は山場を越したようで、歩行も飲食も、それなりにできるようになってくる。変わって、今度は手の発疹がひどくなってくる。手は足と違って、痛いより痒い。上半身全体、発疹の痒みが半端ない。特に入浴後は、全身、蟻に這われてるよう。チクチクするし、とにかく痒い。
7日目、やはりこの日も手と腕がひどく痒い。痒みに「ムヒS」が効くことを知る。手足口病にステロイド含有のかゆみ止めはNGらしいが(免疫抑制作用がウイルスを助長と?)、昔ながらの「ムヒS」は非ステロイド。
8日目~、手の発疹も峠を越したようで、マシになってくる。内ももやお腹の発疹も消えていく。足の発疹跡の皮がむけてくる。
現在16日目、足の皮は今もむけ続けていて、見た目が非常に汚らしい状態に。早く脱皮完了して欲しい。そして手のひらも、ついに皮がむけ始めてきた。これまた不潔な見た目になるんだろうな。
以上、症例報告までに。これから爪が剥がれたり、まだまだホラーあるらしいけど、ひとまず大人の手足口病はなるもんじゃないです。皆さんも、手洗いうがい、こまめにしてくださいませ。
(しゃっくり10日止まらずの記事以来だな、病気ネタ。)
追記、このあと両手両足20本の爪が剥がれました。全てが元の身体に戻るまで一年はかかりました。